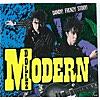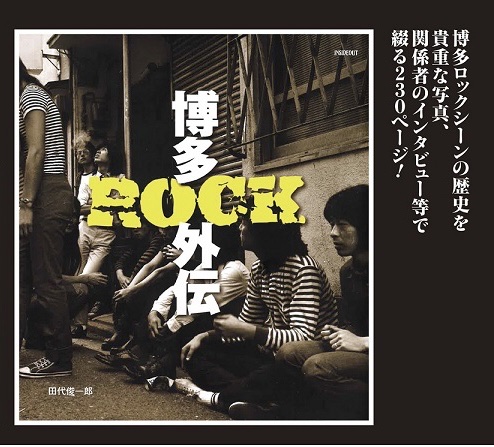
こんばんは。デラシネ(@deracine9)です。
本日は、めんたいロック特集の第2弾。
天神の「照和」、博多の「ぱわぁはうす」閉店後に活動した、80年代のバンドにスポットを当ててお送りします。
それでは1曲目。
ヌーベルバーグにつまづいて モダン・ドールズ
モダン・ドールズ。
1978年結成。
ヴォーカルの佐谷光敏を楽曲のコンポーザーとして、ファンのあいだでカリスマ的人気を誇った。
モッズやロッカーズなどと並んで、博多ロックの中心にいた。
吉川晃司、BOØWY に影響を与えたとも言われる。
80年代の音とは思えない、洗練されたヴィジュアル系の元祖とも言えそうだ。
ビートの効いたファンキーなサウンドもあれば、ダンサンブルで、メロディアスな曲もある。
このバンドが、なぜ、メジャーデビュー出来なかったのか?
これはちょっと、追究していきたいテーマだ。
歌い方を聴けば、まるで吉川晃司か氷室京介。
こっちが本家なのでは、と思わせる。
この曲のタイトルは、甲斐バンドっぽい。
「ダニーボーイに耳をふさいで」「東京の冷たい壁にもたれて」みたいな感じ。
この頃、甲斐バンドは、ニューヨークで新譜のミックスダウンを行うメジャーバンドだった。
凍てついたサンダーロード モダン・ドールズ
70年代の終焉。
福岡天神の「照和」 と博多の「ぱわぁはうす」は、ほぼ同時期の、1978年に閉店。
多くのアーティストが生まれ、東京へ巣立って行った。
「照和」からは、海援隊、チューリップ、甲斐バンド、長渕剛。
「ぱわぁはうす」からは、サンハウス解散後の鮎川誠、柴山俊之。
彼らの上京によって、バックヤードにいた者たちにも転機が訪れる。
ジューク・レコード店主、松本康。
学生の頃から、ロック喫茶・ぱわぁはうす のスタッフだった松本は、博多ロックを支え続け、その栄枯盛衰を目の前で見てきた。
サンハウス5人のメンバーに次ぐ、六番目のサンハウスとも呼ばれた男だ。
1977年、松本は輸入レコードショップ「ジューク・レコード」を福岡市天神に開店。
70年代後半から活動を始めた次なる世代の胎動を肌で感じ、ライブの開催やインディーズ・レコードの自主制作をサポートし、後方支援を続けた。
そして 80年代、博多ロックはモッズやロッカーズを始めとする次世代バンドを相次いで誕生させ、「めんたいロック」という全国区の知名度を得る。
博多という街が、ローカルでフランクであるがゆえに、生粋のロック・スピリッツが擡頭する足場が存在した。



現在のジューク・レコード 。福岡市中央区、親不孝通り横にある。
フルノイズ LIVE 1982
フルノイズ。
ヴォーカル・井上マサルを中心として結成。
モダン・ドールズと、その時期は重なっている。
このバンドも、博多ロックの中核を成した。
マサルは小学6年のとき、長崎県から福岡市東区西戸崎に引っ越して来た。
リンゴ・スターに憧れて、我流でボンゴを叩いていた。
高校生のとき、照和のオーディションを受け、二度目で合格。
マサルのボンゴは、甲斐よしひろの目に止まり、ハッピーフォークコンテストの優勝曲「ポップコーンをほおばって」の演奏に、臨時メンバーとして加わった。
博多で有名になっても、メジャーになるつもりはなかった。
自分流のロックを貫くこと、それ以外に関心がない男。
出したレコードは、自主制作盤の EP 1枚だけ。
しかし 2001 年、過去のライブ録音が、奇跡的にCD として発売された。
時を超え、2015年から活動を再開している。
生業は、トラックのドライバーだと言う。
偉そうな奴 フルノイズ
1979年に開店したライブハウス、80‘s FACTORY 。
照和、ぱわぁはうす と入れ替わるように、80年代初期の博多ロックを支えたのが、80's FACTORY だった。
店長は、伊藤エミ。
伊藤は「照和」の常連客だった。彼女のお目当ては、月曜日。
看護学校に通いながら、月曜の夜になると寮を抜け出し、最前列で甲斐よしひろがステージに立つのを待ち焦がれた。
そのうちメンバーとも親しくなり、ライブの後の片付けをしたり、メンバー行き付けの屋台「喜柳」にも同行するようになった。
そこから彼女は、博多ロックを支える中心の一人となってゆく。
博多から天神の親不孝通りに進出した居酒屋の経営者・溝上徹思。
彼は、親不孝通りを若者の不夜城にした立役者だった。
次々と若者向けの居酒屋店舗を出店し、親不孝通りのタウンマップを作った。
伊藤エミは客として溝上と知り合い、新しいライブハウスを作るため、日本全国を巡った。
2年の時を経て、伊藤は帰って来た。
オーナーは溝上、現場の店長は伊藤だった。
危険がいっぱい ヒップス
ヒップス。
太田黒恵美は、大牟田市出身。
女性ヴォーカルで、80's FACTORY の仲間たちから生まれたバンド。
のちに、ティーンエイジ・ニュースを結成する。
この曲を聴くと、サディスティック・ミカ・バンドあたりの影響が見て取れる。
女性ヴォーカルのバンドは、この時期から急増した。
伝説のステージと、夢の終わり。
親不孝通り沿いにある長浜公園の北側に、80's FACTORY はオープンした。
80年代博多ロックの伝説が、その場所から生まれた。
シーナ&ロケッツ、山善、モッズ、ARB 、ロッカーズ、ルースターズ、フルノイズ、、モダン・ドールズ、ダイナマイト・ゴーン、アクシデンツ、マーキーズ、ヒップス、ルーズ…。
めんたいロックという名では一括りに出来ない、個性豊かなバンドが、このステージに立った。

現在の長浜公園。80s‘FACTORY は、樹々の向こうに見えるコンビニの横辺りに在った。
開店から、わずか3年足らず。
80's FACTORY は、1982年3月、その終焉を迎えた。
その理由は、なんという事もない。
赤字が続く、という金の問題だった。
博多んもんのロック、すなわち、祭りだけでは食ってはいけん。
それは、ロック・ミュージックというものに内在する、本質的な問題をはらんでいる。
上昇指向の高い、メジャーへ挑戦するバンドは、いつか東京へ旅立つ。
集客力に優れたバンドが上京すると、やはり客足は落ちる。
地元志向、ピュアなロックテイストを追い求めるバンドは、博多で活動を続ける。
だが、本命がいないマネーゲームに、打ち克つバンドは多くはない。
いずれにせよ、ロックは転がり続ける事、時代に叛旗を翻す事、それができなくなれば、終わる。
THE MODS の森山達也が歌ったように、ロックで生きるということは、いつかは負ける「ルーズ・ゲーム」を戦い抜くという覚悟を必要とする。
やがて、夢は終わる。
「祭りのあと」の寂しさが、訪れる。
それこそが、青春そのものと言えるのかもしれないが…。
これも超名曲。
バレンティノ気取って モダン・ドールズ
悲運のカリスマ・佐谷光敏。
モダン・ドールズの佐谷は、40歳の若さでこの世を去った。
まだまだ、彼の音楽人生は続くはずだった。
それだけの才能に溢れていた。
モダン・ドールズの誤算は、メンバーが固定しないことだった。
その最たる出来事が、ギターとドラムスのモッズへの移籍だった。
ロンドン・レコーディングによるメジャーデビューという華々しいモッズのブレイクに、佐谷は何を思っただろう。
佐谷のスターとしてのルックスや音楽のセンスは、博多のバンドの中でも飛び抜けていた。
それだけに、負け犬にはなりたくない、なるはずがない、そう思っていてもおかしくはなかった。
カリスマにも焦りはあっただろう。
そして、ついにメジャーに行けなかったという想いが、佐谷を苦しめた事は、想像に難くない。
運と実力。
よくいわれる二つのうち、佐谷には片方が欠けていた。
それは、誰よりも、佐谷自身が知っていたのではないだろうか?

TRIBUTE TO MODERN DOLLZ~ブラインド越しの俺達~
- アーティスト:オムニバス,Trio the 玄界灘,広石武彦,SPACE HORSES,横道坊主,THE PRIVATES,勝手にしやがれ,YAMAZEN,水戸華之介 with King Shows,MODERN DOLLZ
- 発売日: 2002/10/04
- メディア: CD

今も鳴り止まない、音がある。
照和、ぱわぁはうす に次いで伝説となった80's FACTORY 。
その聖地の向かいには、長浜公園を挟んで、今もライブハウスがある。
DRUM ROGOS と DRUM Be 1 。
その場所は、今でも青春の中に燦めく光彩を放って止むことはない。
長浜公園には、今も大勢の若者達がライブを目当てに訪れる。
今ではメジャーになった多くのバンドが、そこでギグを演った。
20年前、私はロゴスで、エレカシを聴いた。
最近では、あいみょんが、2018年3月に DRUM Be1 で、同年12月に、DRUM LOGOS で、ライブをやった。
ローリング・ロックのスピリッツは、今も博多の街で、鳴り止むことはない。
カーテンコールの陰で、鳴り止まない拍手の音と共に、時代の空気の中に息づいている。



80’ FACTORY が在った長浜公園の南側に、ライブハウス・DRUM LOGOS 、DRUM Be 1 がある。親不孝通りにある長浜公園は、今も若者達の溜まり場となっている。
それでは最後の曲。
曲を書いたのは、もちろん、モダン・ドールズの佐谷だ。
インプロビゼーション モダン・ドールズ / ティーンエイジ・ニュース / ザ・シャム / 山善
最後に。
ここに、特筆して紹介したい本がある。
田代俊一郎氏の著作「博多ロック外伝」。
この本は、田代氏が西日本新聞の連載「博多ロックの軌跡」を加筆修正して生まれたものである。
読んで頂いた記事の中に貼っているリンクから自ずと知れると思うが、記事の中のエピソードは、この著作に多くを負うている。
田代氏には、心から感謝申し上げたい。
そして、著作の内容の一部をお借りして、この記事を書かせて頂いたことに、ご寛恕のほどをお願いしたい。
昨年、私はこの本を、「ジューク・レコード」で発見した。
博多のロック・シーンを語る上での貴重な著作に、ずいぶんと刺激を頂いた。
また、店内外の写真撮影をお許し頂いた、ジューク・レコード スタッフの方、及びオーナーの松本康氏には、心から感謝申し上げたい。
松本康氏は、博多ロック・シーンにおけるレジェンドである。
スタッフの方から、現在、健康を損なっておられるとお聞きした。
一日も早いご快復を祈っている。
いつかお元気な姿で、お店でお会いできればと思う。
( 文中の敬称は省略しました。)