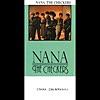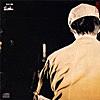こんばんは。デラシネ(@deracine9)です。
本日は、放送禁止歌の名曲選 PART2をお送りします。
この特集の PART1は、すごく反響が大きくて、なぜこれほど、放送禁止歌にみんなが関心を持つのか、ある意味、考えさせられましたね。
今回も、曲に入る前に、森達也氏のドキュメンタリーに触発されて生まれた、2003年に発表の「放送が禁止された歌」(沖縄国際大学 日本文化学科)という相当量の論文がありますので、興味のある方は、以下アドレスをご参照いただきたいと思います。
https://www2.okiu.ac.jp/yamaguchi/houkin.pdf
(2020.11.2 この論文は一時期ネットから削除されていましたが、復活したようです。)
特に興味のない方は、すっ飛ばして、曲を聴いてください。
前回も述べたように、憲法に「表現の自由」が謳われている以上、放送禁止にするのは、あくまでも各放送局の自主規制に過ぎないのです。
しかし、森達也氏によれば、「放送法」という法律の存在によって、「不偏不党」「政治的中立」「公序良俗に反しない」などの放送基準や放送倫理が法的根拠を与えられ、メディアによる表現の自由や報道の自由を制約することに繋がったと言います。
そして1959年に作成されたのが、下の「日本民間放送連盟放送基準」の「内規」なのです。
放送音楽などの取り扱い内規(2004年1月改訂)
放送音楽については、公序良俗に反し、または家庭、特に児童・青少年に好ましくない影響を与えるものを放送に使用することは差し控える。放送に使用することの適否を判断するにあたっては、放送基準各条のほか、次の各号による。
1.人種・民族・国民・国家について、その誇りを傷つけるもの、国際親善関係に悪い影響を及ぼすおそれのあるものは使用しない。
2.個人・団体の名誉を傷つけるものは使用しない。
3.人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別するものは使用しない。
4.心身に障害のある人々の感情を傷つけるおそれのあるものは使用しない。また、身体的特徴を表現しているものについても十分注意する。
5.違法・犯罪・暴力などの反社会的な言動を肯定的に取り扱うものは使用しない。特に、麻薬や覚醒剤の使用などの犯罪行為を、魅力的に取り扱うものは使用しない。
6.性に関する表現で、直接、間接を問わず、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせるものは使用しない。
7.表現が暗示的、あるいは曖昧であっても、その意図するところが民放連放送基準に触れるものは使用しない。
8.放送音楽の使用にあたっては、児童・青少年の視聴に十分配慮する。特に暴力・性などに関する表現については、細心の注意が求められる。
(注記)なお、「要注意歌謡曲」の指定制度は1983(昭和58)年に廃止され、要注意の指定から5年を経過するまでの間、経過期間として指定の効力は継続したが、その期間も1987(昭和62)年に満了し、「要注意歌謡曲一覧表」は消滅した。
つまり、民放で放送禁止になる歌は、この基準のどこかに引っかかっていることになるのですが、最後の「注記」にあるように、すでにこの「内規」を根拠とした「要注意歌謡曲指定制度」は今から30年以上前に、事実上消滅しているのです。
しかし、制度は消滅したが、この「内規」はあるよ、とでも言いたいのか、この「注記」はいかにも言い訳がましく、指定はしないが「内規」に従って判断して下さいねと、放送禁止の制度は各々のメディアに丸投げされただけで、現在も存続している事を示しています。
この事だけでも、自主規制であるはずのものが、事実上は実効性を持っているという歴然たる証拠になるのではないでしょうか?
「内規」のホンモノは、このサイトでご確認ください。
現実に、この「内規」は、番組制作の現場では、強制力を持つものと信じられていた、と森達也氏は証言しています。
また、上記の論文では、リストは消滅したが、2003年の論文執筆当時もNHK 、民放各局には、このような内規は存在していた、との記述があります。
もっとも、最近では以前は決してテレビやラジオで聴けなかった歌が流れたり、ネット配信されたりCD 化されたりと、少しずつ状況はよくなっているようにも思えますね。
これも、時代と共に、古いモラルが棄て去られゆく表れでしょうか?
ここに紹介する歌たちも、ようやく、新しいモラルの登場によって、再び歌われる日がやって来るかもしれません。
しかし、この「内規」のように、曖昧模糊とした、どのようにもコジツケ可能な根拠で、基本的人権である「表現の自由」を奪われる事が許されるのでしょうか?
こんなものがまかり通ったなら、放送禁止は発売禁止になり、事前検閲になり、歌う自由、書く自由をも奪われていくのは目に見えています。
それは、治安維持法によって思想犯が検挙された戦前の日本へ舞い戻り、現在も思想の自由がなく、政府の方針に異議を唱えると、投獄されたり軟禁されたりする中国や北朝鮮のような国になる事を意味します。
私たちは、もっともっと、このような国家権力の動向に、敏感になる必要があるのではないでしょうか?

- 作者: 森達也
- 出版社/メーカー: 知恵の森
- 発売日: 2003/06/06
- メディア: 文庫
- 購入: 17人 クリック: 961回
- この商品を含むブログ (182件) を見る
たいへん前置きが長くなりましたが、ここから曲にいきます。
1曲目。
きょうだい心中 山崎ハコ
この曲は以前にも紹介しましたが、 超のつく名曲です。
収録されていたアルバムは、この曲が放送禁止になったために、幻のアルバムになっていましたが、5年ほど前にようやくCD 化され、陽の目を見ました。
発売禁止になった理由は、近親相姦を歌っているという事です。
つまり、公序良俗に反しているという理由なのでしょうが、歌詞では妹がそれを拒否しており、関係は持っていないのです。
優れた芸術作品というのは、人間というもののあらゆる営みを捉まえ、その真実を探求し表現するものです。
ギリシャ悲劇に「オイディプス王」という古典があります。
この王は運命のいたずらで、知らぬまに我が父を殺し、実の母を妃とするという過ちを犯してしまいます。その後、真実を知った王は、自分の目の玉を抉り、盲目となって放浪の旅に出るのです。
「きょうだい心中」も同じようなものです。
妹の「おきよ」は過ちを犯す前に覚悟を決め、兄に偽って自分を殺すよう仕向けるのです。
優れた芸術は、人間性のあらゆる側面に光を当て、人間とはどういうものか、生きるとは何か、死とは何か、それを自己の表現のスタイルで、作品として結晶化させる事を本分とします。
ですから、旧態依然の社会通念上の道徳やモラルをいったん破壊して、時代と共に移り変わってゆく、人間の新しいモラルや道徳を築く礎となる。
それが、芸術作品の本来の役割なのです。
古い道徳やモラルへの反逆自体が、人間社会への愛情なのです。
この二つの作品は、そういう意味で、本物の芸術作品だと言えるのです。

- 作者: 藤沢令夫
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2018/05/17
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
そもそも、公序良俗とは何でしょうか?
兄と妹、母と子は、近親相姦。
これは、今の日本人にとっては考えられないタブーです。
しかし、血が繋がっていても、いとこ同士の結婚は認めるのです。
なぜ、いとこであれば、許容するのでしょうか?
それは、日本人が社会通念として認めて来た歴史があり、現行の民法でもそれが合法とされているからでしょう。
道徳や社会通念というのは、現在、私たちが生活している共同体の中でのみ有用性を持つ「社会のルール」という便宜的側面を多分に含んでいます。
ですから、普遍の人間性に基づくものとは限らないのです。

- 作者: 芥川竜之介
- 発売日: 2012/09/27
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
芥川龍之介は、こう言っています。
道徳とは、便宜の異名である。
「左側通行」と似たものである。
「侏儒の言葉」より。
そういう現在の社会通念と芸術の関係性を踏まえた上で、このような放送倫理の問題も考えて欲しいものです。
しかし現実には、このような事を主張しても、権力の維持に都合の悪い思想を抑え込む事しか頭にない権力者には、どうでもいい事。
だから私たちは、自分たちの力で、思想の自由、表現の自由などの基本的人権を守ることが大事だと言えるのです。

- アーティスト: 山崎ハコ
- 出版社/メーカー: ポニーキャニオン
- 発売日: 2014/06/18
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (1件) を見る
それでは、どんどん曲に行きましょう。
NANA チェッカーズ
これは、NHK のみの、ダメ出しだったらしいです。
理由は、この歌詞に「わいせつ的表現がある」ということです。
「過去を脱ぎ捨て やろうぜ NANA 」など。
NHK は、ウルフルズの「ガッツだぜ!」を紅白歌合戦で、同じ理由で歌詞を差し替えて歌わせています。
この手の放送禁止に追い込まれた歌には、原由子の「I love you はひとりごと」、おニャン子クラブ「セーラー服を脱がさないで」などがあります。
それにしても、NHK は、チェッカーズ「NANA 」は禁止しているくせに、RC サクセションの「雨上がりの夜空に」は、忌野清志郎に「SONGS 」なんかで堂々と歌わせています。
「おまえについてるラジオ 感度最高」「こんな夜に発車出来ないなんて」。
これが不思議ですなぁ。
個人的には、忌野清志郎ファンでありますから嬉しい限りなんですが、これはなぜOKなんだろう、と思いますね。
車の隠喩にくるんでるからとも、なかなか思えないし。
結局、当時のチェッカーズは、ファン層が10代の女の子だったから。
「SONGS 」はまだ近年の放送で深夜枠であり、清志郎のファン層はオールドだから。
それぐらいしか思いつかないですね。
「NANA 」は、チェッカーズにとって、初めてオリジナルメンバーだけでプロデュースを手がけた、路線変更の曲でしたから、それまでの作られたアイドル路線時代のファンには、十分刺激的なものでした。
NHK も、そう思ったのでしょうかね。

- アーティスト: チェッカーズ
- 出版社/メーカー: ポニーキャニオン
- 発売日: 2016/03/30
- メディア: MP3 ダウンロード
- この商品を含むブログを見る
では次の曲。
おそうじオバチャン 憂歌団
歌っているのは、日本を代表するブルースバンド、憂歌団。
この曲の放送禁止の理由は、何でしょうか?
これが、前回もたくさん取り上げた、差別用語を含む、というやつです。
「おそうじオバチャン」というタイトルそのものが、職業差別に当たるというのだから、ひどいもんです。
こういう理由で禁止になったら、歌えるワーク・ソングは壊滅的になってしまいそうで怖いですね。
ビルのお掃除をしている女性が聴いたら、まあ歌詞がふざけてて、不快に思うかもしれません。こればっかりは、当事者しかわからないところです。
それでも、放送禁止はあんまりだって気がします。
言ってみれば、この歌は、この割に合わない仕事に従属させられている女性の気持ちを、代弁しているとは言えないでしょうか?
オバチャン目線で、低賃金の仕事への不満を爆発させたのが、この歌の本質であって、職業差別とはお門違いではないかな、と私には思えます。
そもそも、ブルースは、アメリカ南部の黒人たちが、糊口を凌ぐための労働の悲哀を歌った事から発祥したと言われています。
こんな曲を歌うからこその、ブルースバンドなんでね。
次の曲。
これは森達也氏の「放送禁止歌」で取り上げられていた曲。
悲惨な戦い なぎらけんいち
動画は上がオリジナル、下がテレビLIVE 変則バージョン。
テレビの LIVE は、最高に笑えます。
これが放送禁止になった理由は、割と明白で、日本相撲協会の圧力を恐れて、各メディアが御意向を忖度したということです。
この曲は、大相撲という日本の大向こうにある権威をおちょくったコミカルソングです。
くどいようですが、憲法にある言論の自由、表現の自由とは、公共の福祉に反しない限り、いかなる権力によっても侵されてはならない基本的人権です。
こういう一般庶民代表のオヤジが、権力者へのささやかな抵抗として、歌という平和的手段で、権力をおちょくる。
それをいとも簡単に、相撲協会の御意向で自主規制をやってしまうメディアは、果たして存在意義があるのでしょうか?
先の国会答弁で一国の馬鹿総理が、自分の言論の自由を主張した。
本来、基本的人権として憲法に謳われている「言論の自由」とは、時の権力者への対抗手段として存在しているものです。
かつての為政者は、権力の発動によって、国民の基本的人権を侵害して来ました。
その歴史の反省に立って、国の最高法規である憲法に、盛り込まれたものです。
それを、内閣府の最高責任者、すなわち総理大臣が「言論の自由」を主張するという、信じられない本末転倒をやらかしました。
安倍晋三は、憲法の成り立ちをも理解もせずに、憲法改正(改悪)を行なおうとしているのです。
現行憲法は、安倍晋三にとっては理解する必要さえ認めていない、戦争が出来る国にしたい安倍自民党に都合の悪い憲法なのです。
しかもそれをしゃあしゃあと、当然のように強弁する。
国を戦争に巻き込む方へと導く首相には、一刻も早く辞めてもらいたいもんです。
あこがれの北朝鮮 タイマーズ
メディアの放送禁止に真っ向から挑戦した、偉大なるアーティストと言えば、まあこの方を置いてほかにはいないでしょう。
キング・オブ・ロック、忌野清志郎です。
その伝説は、下の記事をお読みになれば、十分お分かりかと思います。
この曲もまた、国際関係をややこしくする、ということで目出度く放送禁止になりました。
清志郎は、「君が代」をパンク・アレンジでやったために、これまた放送禁止になりました。
ここまで闘える方は、貴重ですよ。
まさにロック・レジェンドです。
この曲は、上のアルバムに収録されていますが、超レアモノのため、一般庶民には絶望的な価格です。
まず再発も配信もあり得ないアルバムなんで、貧乏人はAmazonのレビューを読んで、youtube の動画を見るのが関の山です。
一般庶民は、安価なメジャーレーベルのアルバムで、偉大な詩人を偲ぶことにしましょう。

- アーティスト: THE TIMERS
- 出版社/メーカー: Universal Music LLC
- 発売日: 2015/10/28
- メディア: MP3 ダウンロード
- この商品を含むブログを見る

- アーティスト: RCサクセション
- 出版社/メーカー: Universal Music LLC
- 発売日: 2005/07/01
- メディア: MP3 ダウンロード
- この商品を含むブログを見る
それでは、最後の曲です。
長渕剛の「静かなるアフガン」。
この国では、歌でアメリカを批判することすら出来ない。
この堂々とした反戦の歌が、放送出来ない。
静かなるアフガン 長渕剛

- アーティスト: 長渕剛,笛吹利明,瀬尾一三
- 出版社/メーカー: フォーライフ ミュージックエンタテイメント
- 発売日: 2002/05/09
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (6件) を見る
昔は、政治と文学の関係について、文壇で、よく語られました。
今は、音楽との関係が大きく問われる時代になって来ています。
昔に比べ、それだけ音楽の力が大衆に影響力を持って来た証拠でしょう。
それを考えるには、長い歴史を持つ文学と政治の関係性に、学ぶことは多いと思います。
私がおすすめするのは、坂口安吾のエッセイです。
坂口安吾の下の本収録「チッポケな斧」は、「チャタレイ夫人の恋人」翻訳出版をわいせつ文書販売罪に問ういわゆる「チャタレイ裁判」について書かれたもので、放送禁止歌問題とも繋がっています。
(不思議なことに、「チッポケな斧」はなぜか青空文庫で公開されていない、数少ない安吾作品の一つです。)
本日は、「放送禁止歌の名曲選。PART 2」をお送りしました。
ここまで長々とお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、おやすみなさい。